この映画の評判がいいのは聞いていた。
しかし、ディカプリオのジェイ・ギャツビーってのはどうにも想像がつかなかった。
あまりに露悪的にすぎるじゃないか、と思っていた。
僕はこの俳優の軽薄な眉間の皺がどうも好きになれなくて、タイタニックにしても、アビエイターにしても初期の出演作そのものの印象が悪くなってしまうくらいなのだが、それがルヘインのシャッター・アイランドの映画化での彼の好演で、お、ワルい顔が板についてきたね、と思っていたので、逆にあのワル顔でギャツビーをやられてもなあ、と思っていたのだ。
しかし、それはまったくの思い違いだった。
原作者スコット・フィッツジェラルドの文章は、言語という不自由で不器用な武器を巧みに操って、あらゆるものを現実よりも現実らしく提示してみせる。
ジェイとニックの出会いのシーンで、ジェイが最初に見せる微笑みをフィッツジェラルドはこう書いている。
「彼はとりなすようににっこり微笑んだ。いや、それはとりなすなどという生やさしい代物ではなかった。まったくのところそれは、人に永劫の安堵を与えかねないほどの、類まれな微笑みだった。」(中央公論新社、村上春樹訳 P92-P93)
この後も、微笑みについての表記が9行にわたって続くのだが、このように書かれた微笑みを「演じる」ってのはどんな気分なんだろうか。
人に永劫の安堵を与えかねないほどの、類まれな微笑みをもし持っていたら、僕の人生が変わりかねないじゃないか。
つまるところそれは、「普通に生きていれば一生お目にかかれないほどの」微笑みという意味で書かれているのだ。
しかし、ディカプリオはそれを「演技して」みせた。
少なくとも僕には、フィッツジェラルドが意図した微笑みはきっとこういうものだったに違いないと、確信できた。
あまりに印象的な表情だったので、鏡の前で練習してみたが自分が嫌いになりそうだったのでやめた。それは別にヤツのせいじゃないが、やっぱりディカプリオは好きになれないな。
今回の映画独自の演出もなかなかいいと思う。
語り手であるニック・キャラウェイが作家志望であったという設定も原作にはないし、狂騒の日々をなんとか生き抜いた後、アルコール中毒と不眠症でサナトリムで療養して、そこでこのギャツビーの物語を書いた、という設定も映画独自のものだ。
ニックという語り手は、原作では、冒頭にある父親の「誰かのことを批判したくなったときは、世間の人が、お前のように恵まれた条件を与えられたわけではない、ということを思い出せ」という忠告を忠実に守って、周囲の狂騒に一歩踏み込まず、自分という存在を固持する存在として描かれている。
だからこそ、騒動のあと一人西部に戻っていくわけだが、映画では、この冒頭の父親の忠告の中核部は注意深く取り去られ、彼自身も深く騒動に取り込まれ傷ついてしまう。
この映画の核心は、この成熟の時代の観客を、現代の映像技術を最大限に(文芸作品には珍しく3Dまで)駆使して、1920年代を象徴する狂乱のパーティーシーンにどこまで引き込めるか、リアルに感じさせるかにあったと思う。
そうまでしているのに、語り手が一歩引いたメンタリティでは、物語がうまく牽引されていかないということだろう。
しかし、ニックをサナトリウムに入れてしまうことで、ギャツビーの精神的な続編とも言える「バビロンに帰る」の喪失感を映画の中に組み込むことに成功しているのだ。
すでに何度も映画化されている「華麗なるギャツビー」をこの時代に再演することの意味を実によく考えてある作品だと感心させられた。
そして全編を印象的に導く「緑の灯火」。
第一次世界大戦で、莫大な富を得たアメリカという国が、目的を見失い、大恐慌が来るまでの10年間繰り広げた狂騒の日々。
そのロスト・ジェネレーションの只中で、ただ愛を信じて手段を選ばず突き進んだジェイ・ギャツビーを導く灯台の灯りが、デイジーの桟橋で輝く緑の灯火だった。
原作では、灯火に導かれてアメリカという新大陸を発見した人々の驚きにまで言及して、この国がどこへ行こうとしているのか、悦楽の果てにある陶酔の未来など現実には来ないのだと、語っているが、さすがに映像的な説得力をもってしても、幻想的に演出された緑の灯火一発でそこまでは表現できない。
そこでパーティシーンに予言的に起用されたのが、ガーシュインの「ラプソディ・イン・ブルー」という楽曲なのだろう。
アメリカは、戦争によって国家としての富は得たものの、積み上げてきた歴史をもたない悲しさで文化面では一歩欧州に及ばないという劣等感を持っており、独自な「アメリカ的」なるものを渇望していた。
ラプソディ・イン・ブルーは、その思いに応えてガーシュインが、移民によって、また奴隷貿易によってできたアメリカという国が宿命的に持っていた文化的な衝突が生み出したブルースを母体に発展したジャズを取り入れた交響曲として仕上げたものである。
アメリカの歴史の浅さへの劣等感を強くはね返していこうとする意志を込めたこの楽曲に、フィッツジェラルドが「華麗なるギャツビー」に織り込んだアメリカへのエールを託したのではないか。
そしてそれに続く、現代的な音楽が、この物語を現代の物語としても認識させる。
ジャズ・エイジもロスト・ジェネレーションも、いつでも繰り返し我々の前に現れるよ、という予言。
この映画はそこまで踏み込んで表現しているような気がする。
さすがにこれだけ奥行きの深い文学作品を、しかもすでに何度も映画になっているものを映像化するのは大変な作業だったと思うが、ディカプリオ氏の名演も含め、実によく出来た映画に仕上がっていたと思う。




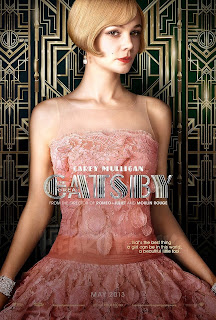

0 件のコメント:
コメントを投稿