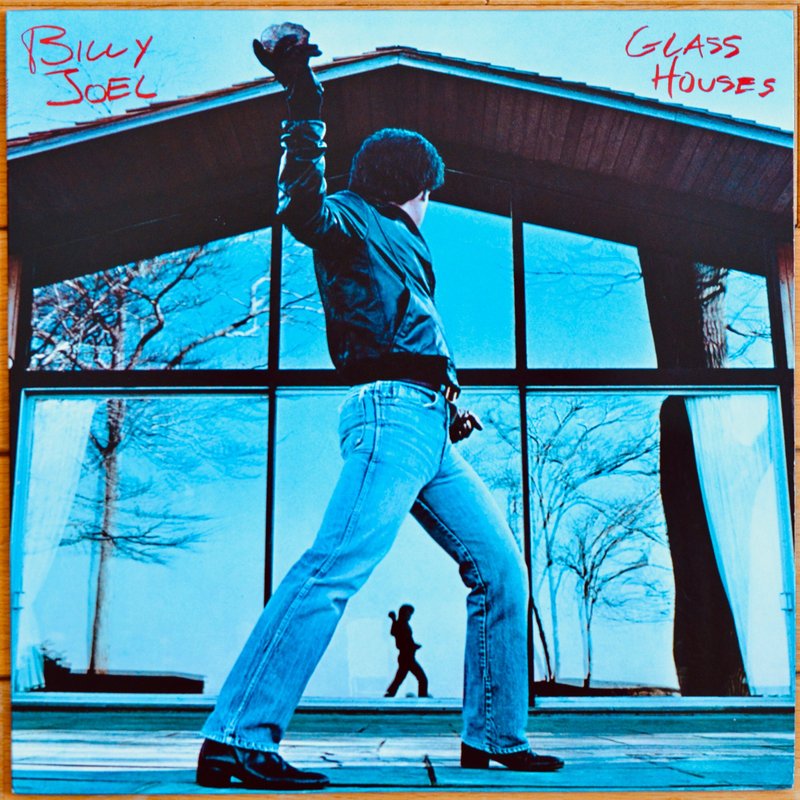1981年リリースのライヴアルバム『ソングズ・イン・ジ・アティック』は、80年のアメリカツアーを収録したものだが、いわゆるライブ実況盤とはいささか趣を異にしている。


ここには、彼のキャリアのターニング・ポイントとなった大ヒットアルバム『ストレンジャー』以降の曲は一つも収録されていない。
このアルバムコンセプトについて、その転回点を作り出した張本人であるプロデューサー、フィル・ラモーンがライナーに寄せた一言を引用しておく。
いくつかの曲は時の流れを超え、常に変わらぬ美しさとインパクトを持ち続ける。一夜にしてスターになることをまだ夢見る人たちへ、これが「ストレンジャー」が私達のレコードコレクションに加わる遥か昔に書かれたビリーのソングライターそしてミュージシャンとしての力量を示すサンプルなのだ。
フィル・ラモーンが書いた通り、このアルバムはもっと広範な人にとっての「サンプル」となり、埋もれた名曲であった『シーズ・ガット・ア・ウェイ』をラジオに乗せ、幻となっていたフォースト・アルバムの再リリースに結びつけた。
また『Say Goodbye to Hollywood』も、このライブアルバムをきっかけに再度シングルカットされ、今度はヒットしている。
ビリー・ジョエルのライブをテレビで観た事がある。
弦も切れよとばかりに鍵盤を叩き、ピアノの上に乗ってハンドマイクで熱唱するビリーの姿は「吟遊詩人」のイメージを覆す、ロックンロール・エンターテイナーそのものだった。
そんな彼を支えるバンドとの信頼関係がそのステージを作り上げていたことは疑いようがなく、このバンドを篤く遇した事がフィル・ラモーンプロデュースの第一の功績であったことがよくわかる。